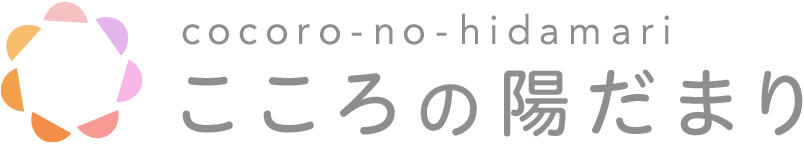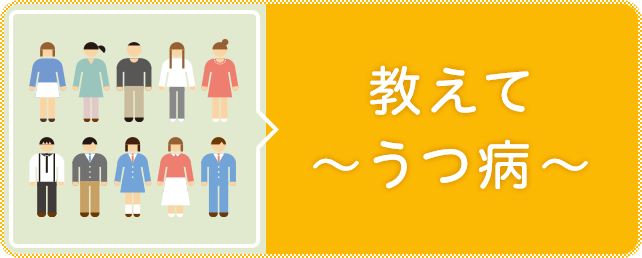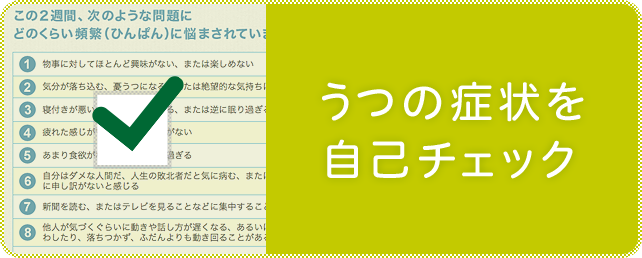監修:名古屋大学大学院 医学系研究科
精神医学・親と子どもの心療学分野 教授
尾崎 紀夫 先生
睡眠と覚醒のリズムを整えていくためには、昼間の活動を徐々に増やしていくことも大切になります。しかし、「昼間に何をやるか?」については、「無理やりやる」、「誰かにいわれたからやる」のではなく、「自分でやれそうだと思うこと」、「やってみたいと思うこと」からはじめてみることが大切です。また、基本は、「やってみようと思うこと」の「半分くらい」からスタートしてみることです。
例えば
- 料理をつくってみようと思ったら
- すべての料理を自分でつくりたくなるところですが、1品だけは自分でつくってみて、他は助けてもらったり、お総菜を買ってくる
- 友達にあってみようと思ったら
- ゆっくり話したいから食事も一緒にしたいところですが、1時間以内のティータイムにする
このようにして何かやってみたあとには、「やってみて楽しめた部分はあるか」、「疲れはどうだったか」ということを自分自身で確認して、また周囲とも相談して、「やってみようと思うこと」の50%(半分)が大丈夫だったのなら次は少し上げて60%にしてみる、無理をしていたようなら50%を40%に減らしてみる、といった調整をしてみましょう。
回復期で大切なことは、最初から100%、完璧を目指そうとせずに、一歩ずつ、そして自分ひとりで抱え込まずに周囲の助けを得ながら進めていくことです。
職場への復帰のシミュレーションをしてみましょう!
もともと仕事をしていた患者さんがうつ病のために休職した場合、「どのようにして職場へ復帰したらよいのか」について、自分ひとりで考えていると、職場復帰がとても大変なことのように思えてきます。これまで一緒に治療をしてきた医師、治療中の生活を支えてくれた家族、そして復帰する職場の方々と相談しながら、復帰への道筋を進めていきましょう。
シミュレーション例
-
STEP 1「そろそろ、職場復帰を考えましょう」と医師にいわれる。
-
STEP 2うつ病になった当時のことを少し整理しておく。
うつ病になった頃の状況を振り返っておくことが大切です。
どのような状況で調子を崩してしまったのかを確認し、復帰したあとに、また同じような状況が起こったとき、どのような対処方法が可能なのかを検討しておきます。例えば、いくつかの問題が重なっていたなら、「優先順位をつけて重ならないようにする」、ひとりで抱え込んでいた場合は「周囲と相談して、抱え込まないようにする」、といった対処方法です。 -
STEP 3可能なら、患者さんと職場の関係者(産業医の先生や上司など)と医師で復帰のための話しあいの機会をもつ。
医師が職場の方と直接話をすることで、復帰したあとの職場状況の確認ができます。「リハビリ出勤が可能か」、「半日勤務からスタートできるか」など職場の状況を知ることによって、復帰する前の治療目標を立てることが可能になります。また、医師の意見を参考に、職場の方による復帰支援を組み立てることもできます。
最近は、職場でリハビリ出勤などの対応がない場合でも、職場復帰に向けてリハビリを行える施設もあります。 -
STEP 4可能であれば、もとの職場に復帰することを前提にする。
「今までいた職場が自分にあわないからうつ病になった」という考え方は、うつ病により物事のとらえ方が否定的になっていた結果によることも多いようです。「今までの職場は自分にあわないところもあるが、仕事としてやれる部分もあるし、仕事仲間として支えてくれる人もいる」という考え方の整理をして、もとの職場で働けることが、その後の患者さんにとっても理想的です。
また、違う会社や部署に復帰しても、そこでの人間関係や職場環境があうかどうかはわからず、新しい職場に適応するためには相当なエネルギーが必要となるため、さらに大きな負担となる場合もあります。
しかし、STEP3の話しあいで、例えば単身赴任中に調子を崩した場合、家族のサポートを復職後に必要とするなど、もとの職場に戻ることが必ずしもプラスに働かないと判断される場合もあり、復職先については周囲の意見を取り入れて、調整してください。 -
STEP 5実際に会社で働き出す。
しばらく休んでいる間に、職場の状況も変化しています。したがって、最初の1か月は「職場の状況がわかること」、そのために「周囲の人に確認すること」を目標にしましょう。また、職場の状況がわかったうえで、仕事をやりはじめたら、6か月かけて本来の自分のペースに戻す気持ちで少しずつ増やしてください。また、少しずつ仕事を増やしていく中で、「今は何をやり、何はやらないのか」という優先順位をつけるようにしましょう。
何より、ひとりで抱え込まずに、周囲の人と相談しながら進めていくことが大切です。